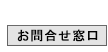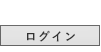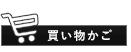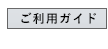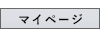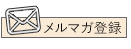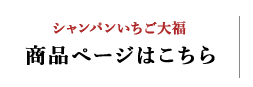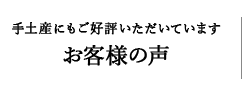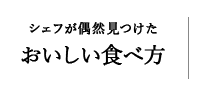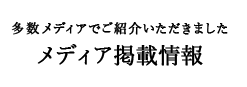人生で一度は食べたい、絶品『和菓子』 - 和菓子の楽しみ方や知識・文化まで合わせてご紹介

手土産など余所いきな気品もあれば、日常のお茶請けとしても楽しまれてきた和菓子。お菓子の中に四季折々の風情が漂い、文化が香る。 ひとくち食べれば、甘みが広がりほっこりとした気持ちにさせてくれるような、安らぎもある。 和菓子には、そんな品格と懐かしさの両方があります。 今回は、『人生で一度は食べたい、絶品の和菓子』をご紹介しつつ、和菓子の魅力をお届けできればと思います。
和菓子の代表的な種類
おいしい和菓子のご紹介に入る前に…まずは、和菓子の種類・分類を簡単にご紹介。 「和菓子の中には、どんなお菓子があるの?」ということが、ざっくりとでもイメージできるようになるかと思います。 和菓子は、大きく分けて『朝生菓子』『上生菓子』『半生菓子』『干菓子』の4種類。
- 朝生菓子
-
朝生菓子は、作ったその日に食べる和菓子です。代表的な朝生菓子は、大福・団子・草餅など。 多くの方にとって馴染み深い和菓子の種類です。
- 上生菓子
-
上生菓子は、繊細な技巧を凝らし、季節の風物を表した煉切り(練り切り)などが含まれます。 「生」菓子とは言いますが、お饅頭(まんじゅう)のように蒸して作るものや、どら焼きなどの焼いたお菓子も含まれます。多くは、2~3日はおいしく食べられる和菓子です。
- 半生菓子
-
半生菓子は、前に紹介した「生菓子」と次に紹介する「干菓子」の中間に位置するお菓子。 京都が発祥といわれ、生菓子に比べて小ぶりなことから「一口物」とも呼ばれます。一般的には、おいしく食べられる期間は30日〜120日ほど。 代表的な半生菓子は、最中(もなか)・羊羹(ようかん)などがあります。
- 干菓子
-
干菓子は、火を加えたり乾燥させたり砂糖で漬けたりして、日持ちするように水分を抜いたお菓子。 お煎餅・落雁(らくがん)・金平糖(こんぺいとう)などが代表例です。
賞味期限は、一般的に上の方が早く、下にいくほど長くなっていきます。手土産などの贈答の品を選ぶときなど、相手方の人数や食べられる場面にあわせて選び際の参考になるかと思います。
人生で一度は食べたい、絶品の和菓子
ここまで、和菓子の基本的な分類を見てきました。 和菓子を知る上では大事なことではあるのですが、やっぱり、一番知りたいのは「おいしい和菓子」について。 ここからは、『人生で一度は食べたい、絶品の和菓子』をご紹介していきます。
丸い姿が愛らしい。『大福』
和菓子といえば…ときかれると、『大福』と答える人も多い人気の和菓子。 王道から通好みの逸品、フルーツを使ったものまで。丸く愛らしい姿も愛らしい、おいしい大福をご紹介いたします。
伝統と歴史の重みとともに。『羊羹(ようかん)』
見た目は地味かもしれませんが、伝統と歴史に裏打ちされた羊羹(ようかん)は、『間違いない』贈り物としても人気です。
釣ってはいないけど、天然もの?『たい焼き』
たいやきファンの間では、1匹ずつ焼いたものを「天然もの」、複数匹を一回で作れる型で焼いたものを「養殖もの」と分けて呼ばれることも。 職人が1匹ずつ焼き上げる「天然もの」の名店をご紹介。
香ばしい皮の香りが立ちのぼる。『どら焼き』
焦がした砂糖のキャラメリゼされたような香りや、生地の香りがお店の中にあふれる。どら焼きを焼いているお店には、焼き立てのパン屋さんにも似たワクワクとさせてくれるような香りの魅力があります。 店舗に足を運んで香りとともに味わってみたい、そんな『どら焼き』をご紹介。
庶民のお菓子から、伝統和菓子の一角に。『きんつば』
『きんつば』は、あんに小麦粉を水で溶いた衣(ころも)をまとわせ、焼き上げる和菓子。 焼き上がると衣(ころも)が薄い皮となり、皮とあんこの味わいが楽しめます。上品な甘さで、一年を通して手土産や贈り物としても人気です。
パリっとした皮としっとりあんこのハーモニー。『最中(もなか)』
パリっとした皮があんこの味わいを引き立てる。和菓子の中でも、ひときわ食感のコントラストが楽しいお菓子です。
年中行事と和菓子
ここまで、『人生で一度は食べたい、絶品の和菓子』をご紹介していきました。 ここからは、季節の行事に合わせて楽しまれることも多い和菓子の話をご紹介していきます。 雨を詠い、虫の声に耳をかたむけ、草花を愛でる。 日本では、古くから四季の移ろいを楽しむ文化があります。 それは、和菓子でも同じ。季節の素材や色で、四季の移ろいを表現し、見て、香って、食べて、楽しむ文化が根付いています。 ここでは、そんな和菓子と年中行事をご紹介していきます。
正月(1月)と鏡餅・花びら餅

お餅は古くから神聖なものとされ、お祝いごとに欠かせない存在でした。 新しい一年が始まるお正月に、鏡餅を供えるのは今でも変わらない習慣になっています。 他にも、京都のお正月の定番となっている和菓子が「花びら餅」。 あんと牛蒡(ごぼう)をお餅で包んだ一見するとミスマッチにも思える和菓子なのですが、食べてみると不思議な一体感のある味わいが広がります。 牛蒡(ごぼう)が使われている理由は、おせちを想像してみるとわかりやすいかもしれません。 牛蒡(ごぼう)が土の中にしっかりと根を張るので「家の土台がしっかりしている」ことや「長寿」を願う気持ちから、おせち、そして「花びら餅」の具材にもなっているのです。
桃の節句(3月)と菱餅・雛菓子(雛あられ)

ピンク・白・緑の三層の菱餅やカラフルな雛あられなど、桃の節句にはかわいらしい色合いのお菓子が並びます。 もともとは厄を払い長寿を願うという意味合いが込められており、不老長寿の象徴でもある『桃』が節句やお菓子のモチーフになっています。 桃が不老長寿の力を持つという話は、例えば、『西遊記』でも有名な孫悟空のエピソードにも。 孫悟空は、天界から蟠桃園(ばんとうえん)の管理人に命ぜられます。 蟠桃園には、三千六百本の桃の木がありました。 手前の千二百本は、三千年に一度だけ熟し、これを食べたものは仙人になれる。 中ほどの千二百本は、六千年に一度だけ熟し、これを食べたものは、長生不老が得られる。 奥の千二百本は、九千年に一度だけ熟し、これを食べたものは天地のあるかぎり生きながらえるとされていました。 孫悟空は、この一番奥の九千年に一度だけ熟す桃を盗み食いしたことで投獄されてしまいます。 その後、孫悟空は改心して天竺へ旅する三蔵法師のお供をすることになる。というのが、孫悟空と三蔵法師の旅の始まり。
端午の節句(5月)と柏餅(かしわもち)・粽(ちまき)

端午の節句に柏餅が食べられるようになったのは、江戸時代からといわれています。 柏の木の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちないことから、新芽を子ども、古い葉を親に見立て「子孫繁栄」「家の繁栄」の象徴とされてきました。端午の節句(男の子の節句)の日には、そんな願いを込めて、柏餅が食べられるようになったのだといいます。 粽(ちまき)は、端午の節句の行事とともに中国から伝わったもの。楝樹(せんだん)の葉で米を包むことで厄除けとしたことが、粽(ちまき)の始まりとされているようです。
お彼岸(3月・9月)とおはぎ

春は春分の日、秋は秋分の日を中心にして、その前後3日間をあわせた7日間がお彼岸です。 旧暦では、この日を境に、厳しい冬の寒さと汗ばむ夏の暑さに別れを告げる、新しい季節の始まりの日となっていました。 それぞれを分けて、春のお彼岸を「春彼岸」、秋のお彼岸を「秋彼岸」と呼ぶこともありますね。 そんな「お彼岸」に親しまれてきた和菓子が、「おはぎ」です。 小豆の赤色には、災厄をはらい福をもたらす考えがあり、お彼岸にお墓参りなどをして先祖を供養する習慣と思いが結びついたともいわれています。 ちなみに、春のお彼岸に食べる「ぼた餅」と秋のお彼岸に食べる「おはぎ」は同じもの。 夏は「夜船」、冬は「北窓」。おはぎの風情。 「ぼた餅」と「おはぎ」。材料に使われる小豆の形が、春に咲く「牡丹(ぼたん)」の花に似ていることから春は「ぼた餅」、秋の花である「萩(はぎ)」の花に似ているため、秋に食べるものは「おはぎ」と呼ばれるようになったというのが一般的な名前の由来です。 また、おはぎのお餅は、お餅を杵で「つかず」に潰すようにこねて粗めに仕上げるのが特徴のひとつ。いつお餅をついたかわからずに出来上がっていることから、「搗(つ)き知らず」と呼ばれるようになりました。 そして、この「つき知らず」から転じて、暗い夜には船がいつ着いたかわからない「着(つ)き知らず」から、夏の「夜船」という呼び方が生まれました。 冬には、北向きの窓からは月が見えないため「月(つき)知らず」から、冬は「北窓」と呼ばれるようになったようです。 同じ和菓子でも季節の花や言葉あそびを交えて呼び名を変え、春夏秋冬を楽しむ。 日本ならではの風情が感じられるようですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか? 今回、『人生で一度は食べたい、絶品の和菓子』と、和菓子に関する豆知識やエピソードをご紹介してきました。 このコラムをきっかけに、おいしい和菓子に出会えたり、興味を持って探したり、和菓子のことがより身近になれば嬉しい限りです。